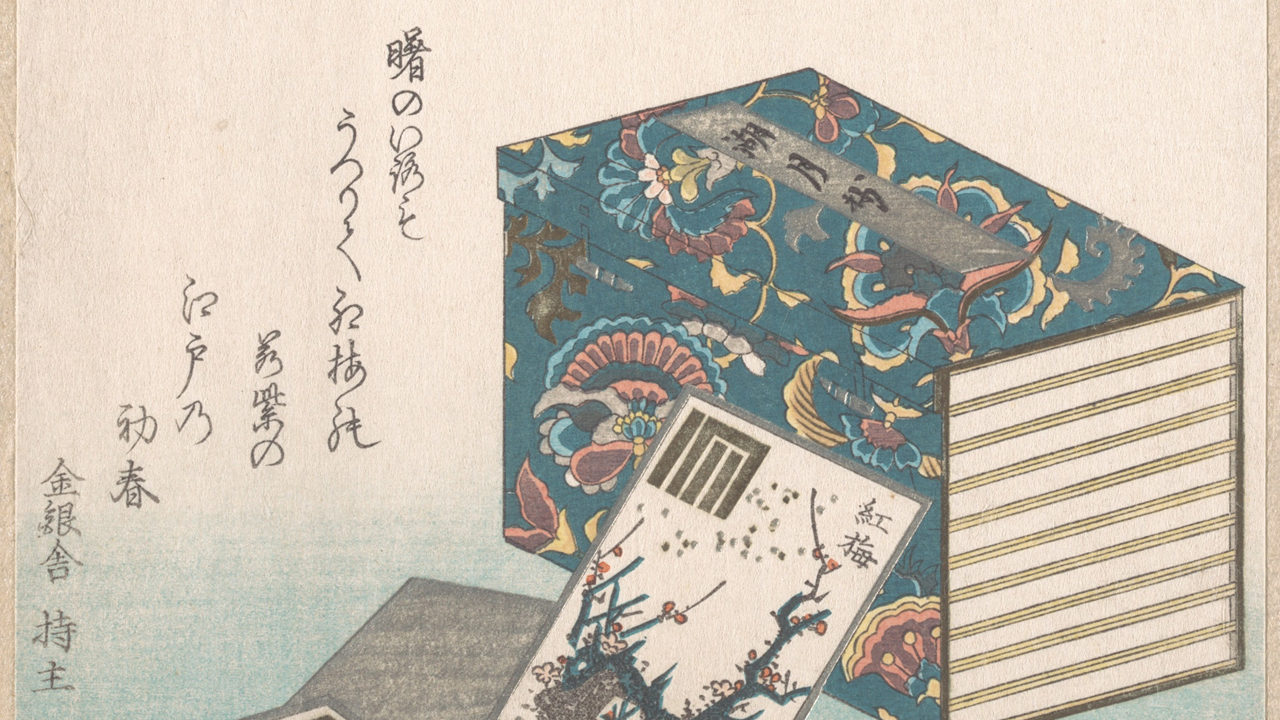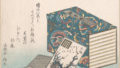光源氏と言って、名前ばかりが大げさで、いろいろと失敗も多いのに、 秘密にしていた色恋沙汰を語り伝えた人はなんとおしゃべりなことか。でも実のところ、源氏は世間を憚っていたのだから色好みの面白いお話などはないのである(語り手の口上)。
長雨で晴れ間がない頃、源氏は宮中に長く留まっている。大殿(左大臣家、葵の上の邸)で(葵の上の兄弟である)頭中将は源氏に心やすくふるまい、学問も遊びも一緒にして心の中の思いも隠さず、というように親しくしていた。
五月雨が降り続いて、しめやかな宵に、源氏は宮中の宿直所で読書などをしていると、頭中将がやってきて世の女性たちについて語り始める。そこへ左馬頭と藤式部丞といった人たちが物忌みにやってくる。二人とも男女の風流事に通じているので、中将は招き入れ、この品定めの議論となる。聞き苦しいことも多い。
「雨夜の品定め」が始まる。
頭中将の論。女性の上・中・下三階級について。
左馬頭の論(一般論として)。
妻として頼れる人を選ぶのは難しい。妻というものは欠けては困る大事なことが多いから。あまりにも情趣に傾いてしまう(実際の生活から離れてしまう)、これが最初の難である。と言って、実直一方で打ち解けた世話ばかりというのも困る。
(こうなってはもう、)身分や容貌はおいて、ひどくねじくれた感じでさえなければ、ただひたすら実直で静かな心を持った女性を終生の頼み、妻とするのがよいでしょう。うわべの情趣は自ずからついてくるでしょうから。
左馬頭の論(比喩論として)。
いろいろなことに喩えて考えてみて下さい。
木の道の匠がその場の遊び物をしゃれた感じで作って、それは目をひいて面白く思うこともある。しかし、調度で決まった様式のものを作り上げるとなると、名人の作は誰が見ても見分けられる違いがある。
また、宮中の絵所には名人がたくさんいるが、普通の山や水の流れなど、親しみやすい事物を描いたものは、名人は格別で、一般の絵師は及ばないものだ。書を書くにしても、深い素養なく気取って書いたものは本格的な筆遣いで丁寧に書いたものと比べたら見劣りする。技芸でさえこうなので、人の、見せかけの情趣などはあてにならない。
左馬頭の体験談。「指喰いの女」
まだ身分が低かった頃、愛しいと思う女がいた。ただ容貌がさほど良くないのもあって、妻にとは思わなかった。あちこち他の女のところへも出歩いていた。この女は自分の至らないところを努力して、まめやかに世話をしてくれた。素直で優しさが身についていった。ただ一つ、嫉妬深いということが難点であった。あるとき喧嘩となって、女は指に噛みついた。もうお別れだと家を出てきた。そうは言いつつ、本当に別れるつもりはなかった。自分を見捨てるようなことはないだろうとたかをくくって、意地を張っているうちに女は思い嘆いて亡くなってしまった。妻ということならばあの女くらいがよかったのだと今となっては思う。どんなことも相談しがいのある女で、染め物、仕立物の腕前も見事なものだった。
左馬頭の体験談。「浮気な女」
同じ頃、歌や書をよくし、琴もうまい見た目の良い女のところへも通っていた。指喰いの女の方をふだん向きに、この女とは秘密に会っていた。指喰いの女が亡くなってからは、派手なところ、艶っぽいところが目についてきた。この女には別に心を通わせていた男がいたようだ。いかにも風流な、二人のやりとりの場面を目の当たりにしてしまった。ときどきの相手が風流なのはいいが…その女とはそれきりにした。
この二つの話を思い合わせると、情趣や風流ばかりでは、相手として頼りにならない。そういう女には、ご注意なされませよ。
頭中将の体験談。「内気な女」
私は、引っ込み思案で愚かな女の話をしましょう。内緒で会い始めた女が、忘れがたい者と思うようになった。この女には親もなく、とても心細そうな様子で、私を頼みにしているのが可愛かった。ところが、女がおとなしいのをよいことにして、長く訪ねなかったところ、私の妻から心ないことをそれとなく言われていたのだった。会いに行ったところ、恨めしい様子も見せず紛らわしていたのに気を許し、また途絶えを置いたところ、跡形もなく姿を消してしまった。まだ生きていたならば、はかなくさすらっていることでしょう。可愛い子もいたのですから、どうにかして探し出したいと思っているのですが。
式部丞の体験談。「博士の娘」
まだ文章生だった頃のこと。たいへん賢い女の例を見ました。ある博士の娘です。女は寝覚めの語らいにも学問を教えてくれ、その女を師として私も漢文が書けるようになった。それには恩があるが、心許した妻とするには…。長い間訪ねないでいたが、何かのついでに訪ねてみたら、いつものところでなく物越しの対面であった。この賢女は、風病が重く極熱の草薬(にんにく)を飲んだため、臭いから会えないという。――君たちは驚き呆れ、作り話だ、と言って笑う。
左馬頭によるまとめ。
すべて男でも女でも、大したことのない人間は、 わずかに知っていることを残りなく見せ尽くそうと思ってしまう。すべてのこと、折と時とをわきまえられない頭では、気取ってみたり風流ぶったりしないのが無難でしょう。
――こうした話を聞きながら、源氏の君はただ一人のありさまを心に思い続け、胸のふさがる思いである。
雨夜の品定めの翌日。【ここから空蟬の物語】
源氏は大殿(左大臣家)に退出したが、妻葵の上のあまりにきちんとしすぎた姿に打ち解けられない。その夕、方向が悪いと言って、方違えをせねばならないと言われる。親しく出入りする紀伊守の邸の場所がよいということで、ひっそり出かけることにする。
源氏は紀伊守邸の様子を眺め、昨夜の話の「中の品」というのはこのようなあたりか、と思い出す。その日は紀伊守の父伊予介の後妻も来合わせていた。この女はかつて、入内も考えていた娘であったが、今は年老いた伊予介の後妻(紀伊守の継母)となっているのである。
源氏は眠れずに、この女(空蟬)の寝所へしのぶ。自邸に帰った後も寝られず、これが昨夜の談義にあった目やすくたしなみある中の品の人か、と思い合わせた。
その後も源氏は空蝉の弟、小君をいつもそば近く連れて、空蟬への文を常に寄せていた。ちょうどよい折の方塞がりを待って、再び紀伊守邸を尋ねるが、身の程を思う空蟬は、源氏には逢うことを拒む。源氏は眠れず、思うようにならない女の心が気高いのをねたましく、またそうだから心惹かれるのだと思う。